会議で質問したものの…
・「それって、今議論していることと関係あります?」と言われる
・質問しても、議論が進まない
なんてことは社会人になるとしょっちゅうですよね…
「会議では質問力が大事」とよく言われますが、いい質問とは何かを意識できている人は意外と少ないものです。
本記事では、「いい質問」の条件と、それを実践するための具体的なコツを解説します!
一朝一夕では身に付きませんが、毎回の会議で少しずつ意識するだけで、質問の質が着実に変わっていきますので、ぜひ参考にしてください。
「いい質問」とは?
まず、そもそも「いい質問」とはなんでしょうか?
「いい質問」を定義してみましょう。
① 具体的かつ本質的である
いい質問は、具体的で本質的である必要があります。
質問が抽象的すぎると、相手は何を答えればいいのかわかりません。
また、議論の本質に迫る質問ができると議論が深まります。
NG例(抽象的×非本質的な質問):
・「人生で最も大切なものは?」
→ 会議とは無関係。
議論が脱線する。
・「とにかく、この会議で一番重要なことは何でしょう?」
→ 抽象的すぎて、相手が何を答えればいいか分からない。
他の人がこういった質問をしていると、すぐに気づけますが、自分の質問がこうなっていることに気づかないのも事実です。
これらは極端な例ですが、意外とやっていることが多いのも事実ですので、一度自分がした質問が抽象的になりすぎていないか?本質的なことじゃないか?を振り返ってみましょう。
OK例(具体的×本質的な質問):
・「このプロジェクトの成功要因は何ですか? 逆に、失敗するとしたらどこにリスクがありますか?」
→プロジェクトの成功のために、本質を突いており、具体的にどこに気をつけるべきかも聞けている。
・「プロジェクトの進捗を妨げている最大の課題は何ですか? それを解決するために、最も効果的な施策は何でしょうか?」
→どこがボトルネック(本質)か、何が解決策(具体)になるかを聞けている
上記のように、その結果に至った要因やどんな課題があるかを聞けると具体的かつ本質的になっていきます。
上記の例ではまだ抽象的ですが、この質問を皮切りに要因や課題を「なぜ?」「どうやって?」と深ぼったり、「こういう側面から見ると…」のように異なる角度から見た場合の要因を深ぼるとさらに議論が深まります。
このように、相手が具体的に答えられる質問が「いい質問」です。
② 相手が話したくて、みんなが聞きたい質問
質問する相手が話しやすく、他の聞き手が「なるほど!」と思える質問もいい質問です。
会議や講義では「話し手が伝えたいこと」と「聞き手が知りたいこと」がズレていることがよくあります。
そのズレを解消する質問をすることで、議論が活性化します。
例えば、営業部長と担当職では、関心のあるテーマや視点が異なります。
- 営業部長の関心:営業戦略、売上目標の達成、チーム全体のパフォーマンス、競合との比較、会社全体の方向性
- 担当職の関心:個々の案件の進め方、営業手法、日々の業務の改善、KPIの達成方法
したがって、部長に質問する際には、単に「自分の業務の疑問を解決する質問」ではなく、部長が話したくなるテーマであり、かつ他のメンバーにとっても役立つ質問が「いい質問」となります。
よくない質問例(個人的な関心のみ):
- 「私の担当しているA社の案件、どう進めたらいいですか?」(個別の案件に限定されていて、他のメンバーにとって学びが少ない)
このような質問はチームメンバーが揃った会議の場ではなく一対一の時に聞くのがいいでしょう。
いい質問例(部長が話したくて、チームにとっても有益):
- 「今期の売上目標を達成するために、部長が今、最も重要だと考えている施策は何ですか?」
→部長の視点を共有でき、チームの行動指針になる - 「過去にチーム全体の営業成績が大きく伸びたとき、どのような取り組みが成果につながりましたか?」
→成功事例を学べることで、チーム全体に応用できる
「相手が話したいこと」と「みんなが聞きたいこと」がいい質問となります。
③ 文脈と相手の経験世界に沿っている
いい質問は、場やタイミングなど文脈に沿った内容であり、相手の知識や経験に合っていることが必須です。
相手の知識・経験を無視した質問は、答えにくく、議論がかみ合わなくなります。
また、会議の流れに沿った質問をすることで、スムーズな議論ができるようになります。
例えば、以下のような登場人物がいるとします。
- 部長(Aさん):新規開拓に強みがあり、過去に〇〇業界で大手顧客を獲得した経験を持つ。現在は営業全体の戦略を考えている。
- 担当者(Bさん):現在、新規顧客へのアプローチ方法に悩んでいる。ルート営業の経験が長く、新規開拓の成功体験は少ない。
この際の悪い質問といい質問は下記のようになります。
悪い質問の例:
・「私は今、メール営業をしているのですが、全然反応がありません。どうしたらいいですか?」
→ Bさんの視点だけの質問。
Aさんが電話や対面営業を得意としていた場合、この質問には答えにくい可能性がある。
・「部長、最近のSNSマーケティングのトレンドってどう思いますか?」
→ 営業部長はSNSマーケティングの専門家ではない可能性が高く、適切な回答が得られない。
・「今の新規営業って、やっぱりインフルエンサーを活用するべきですか?」
→ 部長の経験とは関係のない話題。マーケティング部なら適切かもしれないが、営業戦略の話とはズレている。
いい質問の例:
・「〇〇業界の新規顧客を開拓するとき、どのようにアプローチを始めるのが効果的でしょうか?」
→ Aさんが過去に〇〇業界で成功経験を持っているため、実体験に基づいた具体的な話が聞ける。
・「部長が以前〇〇業界の大手顧客を獲得した際、初回のコンタクトはどのようにとったのですか?」
→ 相手の経験に沿っているため、話しやすく、実践的なアドバイスが得られる。
・「新規開拓の際、ルート営業の経験をどのように活かせると思いますか?」
→ Bさんの現在の強み(ルート営業経験)とAさんの知識を掛け合わせた質問で、具体的なヒントを引き出せる。
このように、相手から何かを聞き出したいときは、「相手の経験を引き出す質問」を適切な場面・タイミングで行うのがいい質問となります。
※ただし、相談として一緒に考えてもらうのなら、聞き方を工夫すれば質問しても良いでしょう。
「いい質問」をするためには?
それでは、「いい質問」をするための方法を見ていきましょう。
解決策①:5W1Hを活用し、質問の漏れを防ぐ
「いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように」の視点を使うことで、議論の抜け漏れを防ぎ、論点を明確にできます。
質問が漠然としていると、回答も曖昧になり、結局何を決めればいいのか分からなくなることがあります。
「いい質問」の定義「①具体的かつ本質的」でも触れましたが、5W1Hを意識することで、具体的な論点を整理しやすくなります。
シーン①:「新規プロジェクトの発足時のミーティング」
質問:「このプロジェクトの具体的な目的は何ですか? 成功したと判断する基準はどうなっていますか?」
プロジェクトとは、目的を達成すると解散します。
しかし、目的が定まってないのはプロジェクトとは言えないので、その目的(Why:なぜこのプロジェクトができたか?)と達成すべき基準(What)を質問しています。
シーン②:「施策スケジュール策定」
質問:「この施策の重要なマイルストーンは何ですか? どの時点で評価や見直しを行う予定ですか?」
ここでは、スケジュールの確認で、いつまでに(When)何(What)をしないといけないのか、見直さないといけないのかを質問しています。
シーン③:「役割分担」
質問:「このタスクは、誰が責任を持って進めることになっていますか? 他のチームとの連携はどうなりますか?」
ここでは、誰(Who)が誰(Who)と行うのかを質問しています。
上記の例では、わかりやすく「そもそもその仕事は誰が何のためにやるのか?」を題材にしていますが、普段の会議でも5W1Hに漏れがないか確認しましょう。
5W1Hを活用することで、質問の精度が上がり、的確な議論を進めやすくなります。
また、5W1Hを発展させた6W3Hなども活用するのもいいでしょう。
解決策②:前提を疑う質問をする
「そもそもその前提は正しいのか?」を問い直すことで、より本質的な議論ができるようになります。
多くの会議では、過去のやり方や常識に基づいて話が進められます。しかし、それが現在の状況に適しているとは限りません。前提を疑うことで、より柔軟な発想や新しいアイデアを生み出すことができます。
シーン①:「新しいシステム導入の議論」
質問:「そもそも、今のシステムのどの部分が一番問題になっていますか? 本当に新しいシステムが必要でしょうか?」
シーン②:「来年度のマーケティング施策の検討」 質問:「昨年の施策のどの部分が最も効果的だったのか分析されていますか? 今年も同じ手法で成果が出る確証はありますか?」
シーン③:「価格競争に巻き込まれた際の戦略の議論」
質問:「本当に値下げが唯一の選択肢でしょうか? 付加価値を高めて単価を維持する戦略は検討されましたか?」
ここでの注意として、「前提を疑う」場合、抽象度が上がってしまうことです。
「いい質問」は「具体的かつ本質的」であるため、「前提を疑う」ことで抽象度を上げ、他の可能性に具体性を持たせましょう。
前提を疑うことで、より本質的な議論が生まれ、新しい視点を提供できます。
解決策③:質問の目的を明確にする
「いい質問」をするためには、質問の目的を明確にすることが重要です。
何のためにその質問をするのかを意識することで、相手が答えやすく、本質的な議論につながります。
以下は、「質問の目的を明確にする」ためのポイントです。
- 何を知りたいのかを明確にする(例:「コスト削減について」など)
- 相手が答えやすいように焦点を絞る(例:「営業プロセスのどの部分に課題があるか?」)
- 議論を深めるために具体的な要素を加える(例:「過去3ヶ月のデータから見るとどうか?」)
上記は当たり前ではありますが、なんとなくで質問してしまうと意外と目的が曖昧になってしまうことが多いのも事実です。
質問をする前に、「自分はこの質問で何を得たいのか?」を考えることで、より有意義な議論を生み出すことができます。
解決策④:仮説を持って質問する
「いい質問」をするためには、仮説を持った上で質問することが重要です。
何も考えずにただ「どうすればいいですか?」と聞くのではなく、自分なりの仮説を立てた上で質問することで、議論が深まり、相手の思考を引き出しやすくなります。
仮説を持つことにより、
- 相手に「ゼロから説明させる手間」をかけさせない
- 自分の思考プロセスを示すことで、より具体的なフィードバックを得られる
- 質問が具体的になることで、議論の方向性が定まる
効果が得られます。
仮説を持って質問をするためには、以下のポイントを押さえましょう。
- 事前に自分なりの考えを整理する(「この現象は◯◯が原因では?」など)
- 仮説を伝えた上で、相手の見解を求める(「この要因が大きいと思うが、どう思いますか?」)
- 相手の答えを前提にせず、柔軟に考える(「違う観点があれば教えてください」)
このように仮説を持った質問をすることで、相手が答えやすくなり、議論の質が向上します。
まとめ
「いい質問」をする方法を紹介しました。
質問力を鍛えれば、会議での存在感が変わります。
会議で「いい質問」をするコツは、
- 5W1Hで情報を整理する
- 「そもそも?」と前提を疑う
- 質問の目的を明確にする
- 仮説を持つ
質問力を鍛えることで、会議での発言が「的確で役に立つ」と評価され、信頼される存在になれます!
今日から実践して、「この人の質問、すごくいい!」と言われる人 を目指しましょう!
今回参考にした本は、「質問力(著:齋藤孝)」と「「良い質問」をする技術(著:粟津恭一郎)」です。
どちらの書籍も名著のため、詳細が気になる方はぜひ参考にしてください。
「質問」だけでなくビジネススキル・コミュニケーション力の底上げを図りたい方は、実践形式のビジネススクールがおすすめです。
実践形式のため、身につくスピードは段違いです。
周りと差をつけたい方にはおすすめです!
また、オンラインビジネス学習サービスを活用するのも、効率的かつ好きな時間に学べるので、こちらでも周りと差をつけられます。
また、「いい質問」を事前に準備することも可能です。
質問するための事前準備について、以下の記事でも紹介しているので、気になる方はぜひご覧ください。
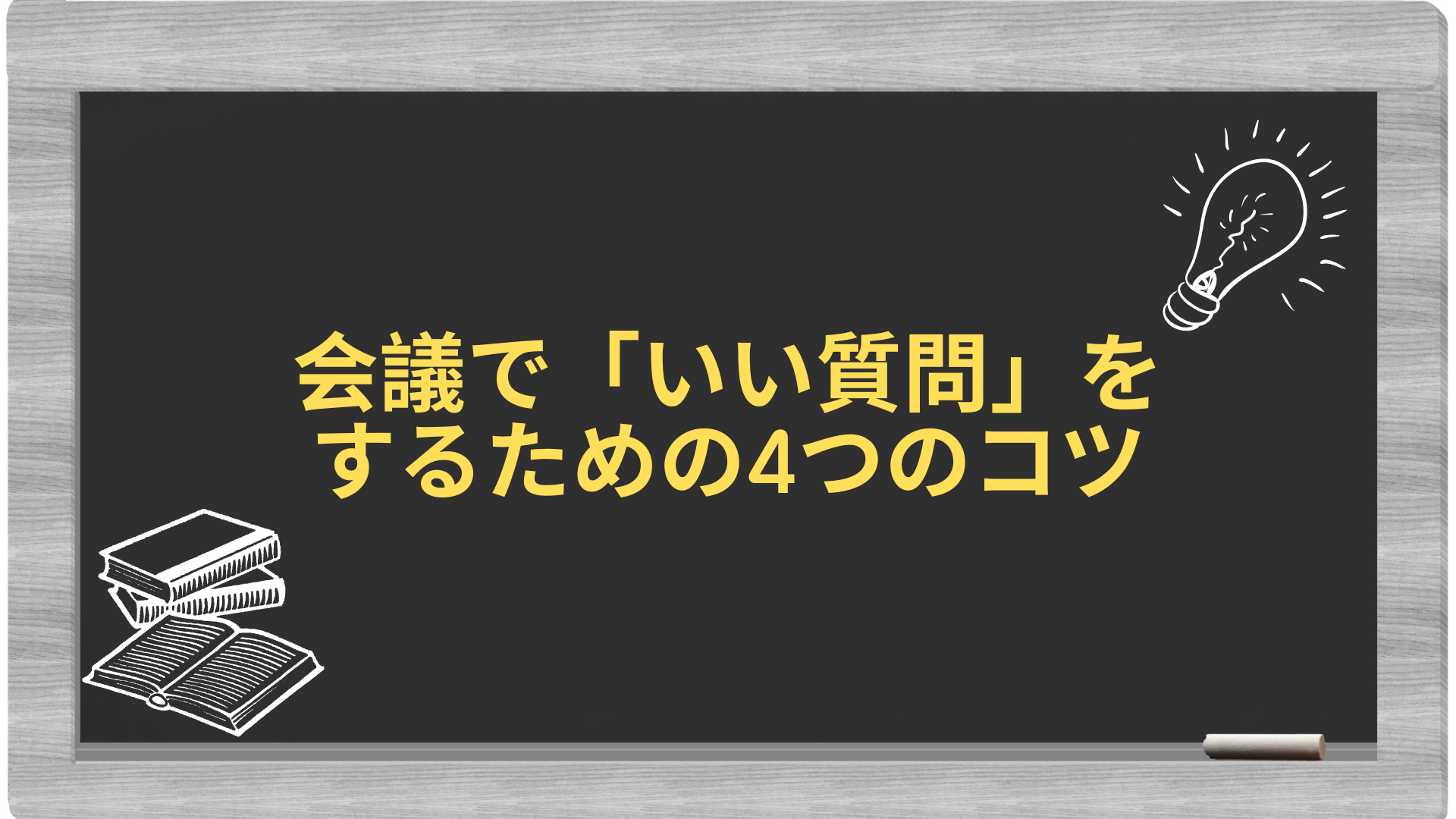
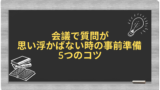
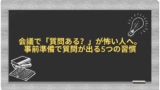


コメント