転職や就活で機械エンジニアに興味があっても、実際どんな業務があるかはあまりわからないですよね。
未経験だとイメージがつき辛いですが、同じく未経験から機械エンジニアとして3年間やってきた筆者の経験に基づいた設計フローを知ることができます。
大小さまざまな治具や装置を開発してきた私が、全体のフローと各工程の注意点をまとめて紹介します。
このページを参考に機械設計ってこんな流れで進むんだなー、こんなこともするのかーていうのを知ってもらえたらと思います!
機械設計の流れ
機械設計の流れとしては以下の通りです。
これだけでピンと来ないと思うので、以下で詳細に紹介します。
① 依頼・要求・要望
これは言葉の通り、他部署や商品開発部など顧客からお願い事が来るところです。
機械設計の顧客は社外はもちろん社内の他部署であるときもあります(配属先により異なります)。
社内だと連携は取りやすいですが、社外だとより設計スキルだけでないいろ知識、スキルが必要になってきます。
ここで、依頼元の要求を抜け漏れなく確認し、どういった機能が必要なのかを固めていきます。
例えば、
「○○を作ってほしい」
と、要望が来た場合、「はいわかりました」ではなく。
・背景
・目的
・コンセプト
・予算
・納期
・機能
・大きさ
・数
など、顧客がある程度決めてくることもありますが、こちらが知っておきたいことはあらかじめ準備し、聞いておくことが重要です。
この辺りは、職場の上司などがやはり経験豊富ですので、何を意識しているかを盗む、聞くのが大事です。
また、慣れてくると、どういった機能がよいのか、本当にその機能・機構でよいのか、こっちの機構の方がコストも下げられるのではないかなど提案も必要になります。
ベテランエンジニアは、そもそもその必要があるかの問題の根本から見直します。
いわゆるなぜなぜ分析で問題を深堀していくことですね。
ここは、ビジネスマンとしての知識も必要となり、かなりの経験も必要になるので、いきなり完璧にするというよりかは、設計段階での各知識、スキルを身に付けることで細かく聞き出すことができると思います。
なので、焦らず、場数を踏みながら、その時々で何が問題になっているか、何を求められているかを見極める力を身に付けましょう!
時には検証してその結果を反映したり、後々新しい情報が出てきたりと設計中に問題が出てくることもあります。
そこで対応できる設計スキルも必要ですが、事前に後戻りしないためのヒアリングも必要です。
一朝一夕では身につきませんが、ヒアリング力を身につける必要があります。
②要求仕様の整理・決定
ここでは①で聞き出した要求について、まとめて、顧客と共有し、仕様を決定します。
ここでまとめることで、さらに抜け漏れをなくします。
①でも抜け漏れが無いようにと書きましたが、設計する立場として疑問に思うことが、まとめる段階で必ず出てきます。
そこで、そのままにせず、顧客とすり合わせることが大事です。
ここは社内と社外で少しハードルが異なりますので、注意が必要です。
要求仕様を整理出来たら、顧客と合意を取ります。
合意を取れるまで、すり合わせをしますが、あまりに何回も聞くのは仕事できない認定を受けるので、少ない回数で効率よく行うことを意識しましょう。
そのためには、自分だけでなく、上司を巻き込んでまとめていくのが良いでしょう。
ここで要求仕様が決定したら、やっと設計に入ります。
③構想設計
構想設計では、細かい寸法や部品の型番や精度を気にせずに、要求仕様に則り、大体のサイズ感、機能や機構をざっくばらんに設計します。
ポンチ絵(ラフ画、漫画でいうネームみたいなもの)や現在では3DCADでのモデルを使って行われていますね。
ポンチ絵は、手書きでも書けますので、①、②での要求仕様の整理でも行うことができ、その場で共有できるのがメリットです。
デメリットとしては、立体の絵の得手不得手、うまくなるのに時間がかかる、変更があると書き直しなどですかね。
3DCADでは、その場でっていうのが少しやりにくいですが、とても見やすいです。
あとは、動作も再現でき、可視化できるので、わかりやすいですね。
デメリットとしては、CADのオペレートスキルが必要、リアルタイムでは追加、編集しにくいなどがあります。
一長一短ではありますが、要求・要望のすり合わせ段階では、ポンチ絵を使い、後のDRには3DCADでのモデルを使用するなどもいいかもしれませんね。
ここで、要求仕様に対して、抜け漏れが無く、機能、機構を設計に反映出来たら次のステップに移ります。
④構想設計DR
DRでは、設計者が考えている機能、機構が合っているか、つまり、認識のすり合わせを行います。
このまま進めていいか、それではだめ、ここはこうしてほしい、ここはこれを追加してほしいなど要望を可視化した状態で確認します。
DRとは何ぞや?と聞こえてきましたが、「Design Review」の略です。
顧客や自部門の先輩エンジニア、上司など関係者を集めて、要求仕様を満たしているかを確認しながら、こんな設計でいいのかの合意を取っていきます。
ここで、新たな課題が出てきたり、要望が出てきたり、そもそも認識が異なると再設計を行い、再度DRを開催します。
また、ここでの概算価格で、コストがほとんど決まります。
価格については、扱う部品の価格や加工品を使用するならどんな加工をするか、それに一体いくらかかるのかを大体でいいですが知っておく必要があります。
ですので、あらかじめ使う部材が決まっているなら、それがどのくらいの価格帯かを調べて把握しておきましょう!
もしコストを聞かれたら多めに見積もっておくことをお勧めします。
大体、はじめてのうちは、後々増えていくので…
もし、思ったより安くなっても、顧客にはお得感を与えられるので、気にせず多めに見積もりましょう!
こんな感じで、ざっくりと全体感を可視化するのが構想設計です。
ここはなるべくサクッと進めておく方が、詳細設計などでかなり時間を取られるので、立てられたスケジュールより巻くイメージでやった方がいいです。
だからと言って、構想設計~構想設計DRのスケジュールをあらかじめ短く設定するのはお勧めしません。
DRが一発で通らないことが多々あるので、スケジュールは綿密に立てましょう!!
⑤詳細設計
詳細設計では、④構想設計DRで決まった内容について、詳細に設計していきます。
もう少し具体的に言うと、
・各部材の寸法
・穴の寸法
・材質
・寸法の精度
・部材の加工方法
・表面粗さ
・ボルト締結の箇所
・ボルトのサイズ
・ボルトの種類
・部材と部材の干渉のチェック
・(動きがあるものは)動きの中で干渉がないか
・購入品の選定
・型番決定
・組立可能か
・電気系統があるなら配線は足りるか、最小曲げRより余裕があるか
などなど、すべてを決めます。
ここで、決めたものがそのまま形になります!
正直、私もCAD上でのモデルでは、ちゃんと組みあがるかめちゃめちゃ不安です。
多分、自分の知識、スキルに自信がつくまではずっと不安です。
しかし、ここでの知識、スキルがエンジニアとしての基礎力になっていくと思っています。
「その設計だと加工どうするの?その加工だと高くなるよね?」
「材質は?それだと重すぎるよ笑笑」
「その板厚だとタップ切れないよ。でも、ナットで締結だと干渉するよね。どうするの?」
など、隅々まで確認します。てか、されます!
詳細設計では、学んだことのアウトプットと新たな学びのインプットの場として最適です。
自分がチャレンジしたいことを盛り込んでもOKですし、これどうやったらいいんだ?ってところはベテランエンジニアに素直に助けを求めてください。
大体何かしらの解決策をもらえます。
そこから学んでいきましょう!!
また、エンジニアとして独自の工夫点を盛り込んでもOKだと思います。
無理に盛り込んだり、コストが高くなったりしては元も子もないですが、構想設計で決まった範疇の中でより便利にしていくことはいいことだと思います。
ですが、あくまで、要求されていることは絶対ですので、やりすぎないように!
⑥詳細設計DR
詳細設計DRでは、構想設計DR同様、詳細設計で決めたことを顧客、部内の上司、先輩を集めて設計内容のすり合わせを行います。
設計した機構、機能に加えて、使い勝手など、すべてについて説明し、フィードバックをもらいます。
特に何もなければ、そのまま進みますが、やはり懸念点やこうした方がいいんじゃないかなど意見をもらいます。
ここで大きく設計変更になることもあります。
「うわーまじか、変更あるのかよー」
て思われたかもしれませんが、発注して組み立ててから、
「あれ?なんかうまくいかないな?」
「組みたたない。。。」
などになったらもう遅いですよね。
それに合わせた部材を買いなおしたり、設計確認して、再購入したりなど後戻りの期間が長くなります。
その分納期が遅れます。
そうすると、顧客へのイメージは最悪ですよね。。。
そうならないためにDRでコメントをもらいつつ、ミスを最小限にすることが重要です。
また、初心者は一発でうまくいかないことがほとんどです。
なので、設計段階のミスはかすり傷です。
気にせず、いただいたコメントは素直に反映していきましょう!!
⑦見積
見積はその名の通り設計した部材の価格をすべて見積もります。
予算以内か、部材の抜け漏れが無いかを確認します。
また、機械設計では加工を加工業者に依頼をすることが多いです。
ここで、一社だけに依頼せず、最低でも3社に加工依頼して見積を取得することが常識となっています(「相見積もり=アイミツ」と呼びます)。
納期やコスト、精度などの要求、過去に依頼したことがある業者なら評判を聞くなどして、最終的にどこに依頼するかを確定します。
高額な購入となる場合は自社の購買部門に依頼することもあります。
てか、ほとんどですかね。
⑧発注・製作
見積で依頼先が決まったら、発注に進みます。
実際に、「お願いします!」てする段階ですね。
発注したら、依頼業者が製作に入るので、納品されるまで待ちます。
待つといっても、やることはあります!
気を抜かないように!!
⑨組立・調整
部材の納品待ちの間に、組図を作成します。
ガンプラの説明書みたいなのを描きます。ガンプラで想像つかない人は、家具の組立図ですね。
カラーボックスだったり、ベッドだったりです。
一つ一つの部品を
・どのボルトを使って締結するか
・どの位置に締結するか
・組立の順番
・部品の区別
・組立の各段階の図
など組立に必要なことは全部描きます。
ここは想像力を最大限使いましょう。言葉で必要な順番を羅列することも有効ですね。
組図を見て誰でも組み立てられるかまで描きます。
部材が納品されたら、組図をもとに組み立てます。
で、組みあがったら動作を確認して、問題がないかを調べます。
ソフトウェアも組み込んだものだったりすると、途中で中断しても問題ないかを各ステップで確認します。電気系統でも同様です。
変に止まったり、予想もしない動きをしないか、穴がないかを確認します。
⑩引き渡し
すべての確認を終え、正常に動作することが確認出来たら、顧客への引き渡しを行います。
手順を説明したり、リスクを説明したり、ケースごとの説明したり、取扱説明書を作成して、それを渡したりします。
ここまでが、設計の一連の流れになります。
お疲れ様でした!
このあともメンテナンスなどはあるかと思いますが、設計としてはここまでです。
関連書籍
今回紹介した工程の詳細については、下記の書籍で紹介されています。
ぜひ参考にしてください。
機械設計の基礎知識を身につけるには以下の書籍がとても参考になります。
先輩エンジニアから代々受け継がれる良書なので、ぜひ一読してみてください。
まとめ
本記事では、構想設計DRまでについて説明しました。
まだまだ足りないことはあると思いますが、ざっくり理解できればと思います。
ブログの質の向上もかねて、質問も答えられる範囲なら受け付けますので、コメントくださればと思います。
各工程で必要な知識の学び方については、「機械設計未経験者必見!独学方法2選!」にて紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
また、機械エンジニアとして転職を考えている方は、職種特化型の転職エージェントに相談してみることをお勧めします。
おすすめは、機械設計や回路設計等の機械系エンジニアに特化した「クラウドリンク」です。
【機械設計&回路設計の転職ならクラウドリンク】新たな経験を積みたい方はぜひ相談してみましょう。
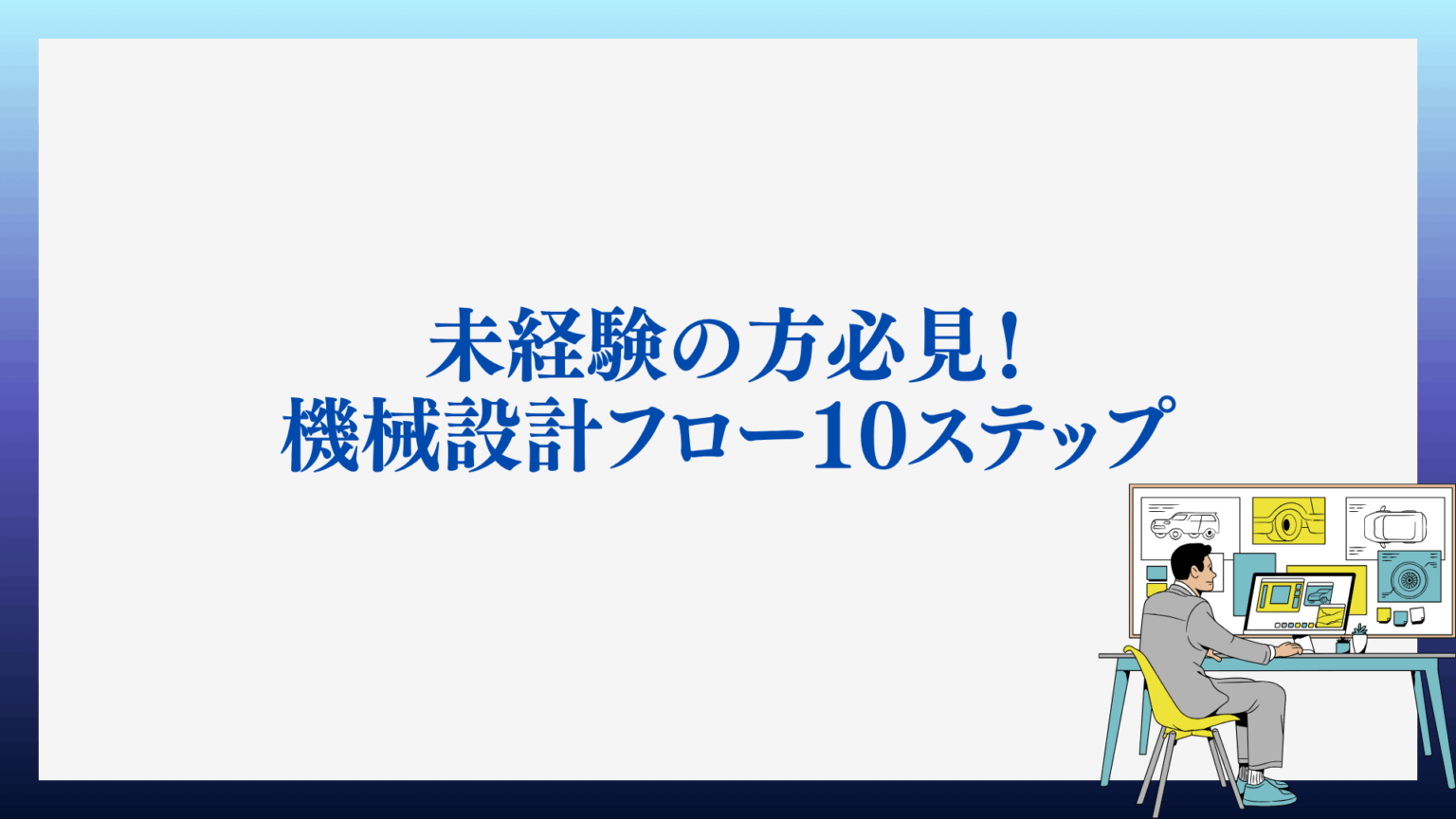
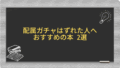
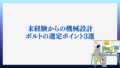
コメント