「こんなに頑張っているのに、なぜ評価されないのか?」──。
昇進は後輩に先を越され、ボーナス額も横ばい。
努力が報われないと、自分の存在意義まで揺らいでしまいます。
実際、私の周りにも毎日定時で上がって、仕事中サボっており、仕事量が少ないのに他の同期より昇進が早い同期がいます…
そんな職場の場合、勇気を持って上司と相談、異動を希望、「今いる職場から離れる」ことが選択肢として挙げられます。
本記事では、評価されない原因を事例を交えて紹介しつつ、そこから抜け出すための解決策を解説します。
最後に、市場価値を知る方法や業界をまたいだ給与水準の比較もお伝えします。
1. 評価されない仕事はキャリアを消耗させる
評価は単なる数字や肩書きではなく、自己肯定感や成長実感に直結します。
正しく評価されない職場に長くいると、仕事への情熱が薄れ、キャリア全体の停滞を招きます。
例えば、
「5年間、残業も休日出勤もこなしてきたのに、昇格は同期より2年遅れ。理由を聞いたら『なんとなくタイミングが合わなかった』と言われた。」
など、職場での評価は、自らの成果・頑張りだけでなく、環境やタイミング、上司の好き嫌い等自分の力が及ばない外的要因によっても決まってしまいます。
このような悪い外的要因が評価に強い影響を与えている場合、いくら働いても評価されずにただただ時間と精神と労力をすり減らします。
2. 評価されない主な理由
あなたが評価されない理由は、①評価基準や制度が不透明、②会社や組織の目標が不透明、③上司や組織文化との相性が悪い、④担当の仕事が軽くみられている、⑤成長機会や成果を発揮する場が少ないのが原因かもしれません。
① 評価基準や制度が不透明
評価基準が定量化されていない場合は、いくら頑張っても明確な目標を立てられず、「達成」が一向にできません。
一度、会社の制度を確認したり、上司に確認するのがいいでしょう。
目標のない仕事は、ただ惰性で働き、無意味な仕事をさせられ、挙句、知識・スキル・ノウハウすべてにおいて何も残りません。
私の会社では、MBO(目標管理制度)によって目標が数値化されて決められています。
そのため、「いついつまでにこれを◯件達成」というのが評価基準となり、取り組むべき内容も明確になっています。
こういった評価基準が明確ではない場合は、会社や上司とすり合わせが必要でしょう。
② 会社や組織の目標が不透明
会社や組織が何を達成すべきなのかが打ち出されていない場合は危険です。
従業員は会社や組織の目標に向かって働くべきのはずが、その目標がない場合、方向性を見失ってしまうからです。
実際に私の職場では、組織の最終目標が数値化されていないため、どの業務にしても「いくら儲かるためにどれくらいの人件費を割くのか」が一生決められず、ただただ時間が過ぎています。
例えば、「売上・利益は多ければ多いほどいい」みたいな目標が組織の目標として掲げられているのは危険です。仕事は、「人員」、「期間」が限られているので、適切な数値目標がないと永遠に消費されるだけになります。
対策としては、わかりやすいのが、会社や組織の『KGI』を聞いてみることです。KGIとは「Key Goal Indicator(重要目標達成指標)」の略で、企業や組織がビジネスで達成すべき最終目標を定量的に示した指標です。
これが設定されることで、個人のKPIを立てられ、それに向かって成果を上げられれば、正しく評価されます。
※KPI(重要業績評価指標(Key Performance Indicator)):最終目標(KGI)達成に向けたプロセスの進捗状況を定量的に把握するための指標
③ 上司や組織文化との相性が悪い
上司が「自分より仕事のできる部下」を嫌ったり、年功序列で若いと成果を出しても評価されないなど、組織文化と合わないといつまでも評価されません。
そういった職場では、成果・実績より制度や感情が優先されているためです。
確かに、経験豊富なベテランの方は仕事がとてもでき、優秀な方も多いのは事実です。しかし、そういった方が全てではありません。
また、人間は感情を持つ生き物です。人と合う・合わないは当然のことでしょう。
しかし、それらと「成果を出しても評価されない」のは、別の話です。
そういった組織は、大概すぐには変われません。制度的に変わったとしても、慣習として続くこともしばしばあります。
年功序列や感情論が一概に悪いとは言えませんが、考え方や働き方、人間関係が合わない場合は、その職場から離れることも考える必要があるでしょう。
きっと、あなたを評価してくれる職場は見つかります。
④ 担当の仕事が軽くみられている
上司が自分の仕事を知らず、そんなに大きな仕事ではない・難しい仕事ではないと勘違いされていないでしょうか?
それはあなたが優秀で、当たり前のようにやりすぎているため、簡単に思われているのかもしれません。
優秀な人ほど淡々と仕事を終わらせますが、その仕事が実際は難しく、引き継ぎが行われた際に初めてその難しさを周りが理解します。
案外、仕事は属人化されていることが多いのは事実です。
DXやシステム化されたものを扱っている場合でも、正しい知識や仕組みを理解するのはそれ相応の努力が必要です。
私も、Webサイトの運用を業務でやっていますが、更新の際のhtmlの編集やシステムの構造を理解しているため、自分では単純作業と思っていますが、周りの人の反応を見ると、「それを理解できるのは才能だね」とも言われます。
あなたもきっとそういった「簡単に済ませているけど実は難しい」ものはありませんか?
エクセルでの関数やVBAを使ったシステム化も貴重なスキルです。
今一度、自分の業務を棚卸して、「こういう業務をこのように工夫して、効率化している」みたいなことを上司と話してみるのがいいでしょう。
上司には普段から細かく仕事内容を伝えておく必要があります。
⑤ 成長機会や成果を発揮する場が少ない
毎日、同じ作業の連続であったり、新たな知識やスキルを必要とする仕事が長年ない場合は、注意が必要です。
人は、人生にとっても、キャリアにとっても、脳にとっても、身体にとっても挑戦することも時には必要で、ストレスに感じることを経験しながらも成長していく生き物です。
新たな刺激がない場合は、成長実感が感じられず、仕事に対するモチベーションが徐々に低下していきます。
モチベーションが下がると、新しいスキルを学ぼうという意欲がなくなり、さらに仕事がつまらなくなり、プライベートにも影響を与えかねません。
こういった職場の場合は、改めて自分のやりたいことを明確にしたり、身につけたいスキルを勉強したりして、異動や転職をしながら成長機会を自ら掴みにいく必要があるでしょう。
このように、評価されない理由は様々です。
外的要因によって評価がされない場合は、これらに当てはまらないかもしれませんが、自分がなぜ評価されないのかを知り、適切な対処法をとらないと、永遠に評価されないままとなってしまい、心身ともに消耗させられる人生になってしまいます。
3. 放置するとどうなるか
先ほども紹介しましたが、このままの状態を放置しておくと、
- 昇進・昇給の機会を逃す
- 市場価値が上がらず、転職で不利になる
- モチベーション低下 → 成果がさらに下がる → 評価が下がるという負のスパイラルに陥る
といったことが考えられます。
もちろん、これらのことだけが人の価値観ではないため、一概に危険とは言えませんが、思い当たることがあれば少し見つめ直してみてもいいかもしれません。
例えば、「評価されないまま7年経ち、気づけば同世代より年収が100万円以上低くなっていた」と言うのはよく聞く話です。
周りと比較することではありませんが、このまま豊かになれないかもしれないと思ったら考え直してみましょう。
4. 対策:社内改善か、社外の市場を試すか
対策として、小さくできる社内での行動と、少し勇気のいる社外での行動を紹介します。
一気に始める必要はありません。
一歩ずつできるところから始めてみましょう。
社内でできること
- 上司に評価基準を直接確認
- 数字や成果物を可視化して提出
- 部署異動や新しいプロジェクトに参加
社外でできること
- 転職市場で自分の評価を確かめる(エージェント面談や求人検索)
- 他社の条件や文化と比較する
- 業界によって給与水準が異なることを知る
- 同じ職種でも、メーカー営業よりIT・SaaS営業のほうが年収100万高いケースあり
- 給与に不満があるなら、勢いのある業界・給与水準の高い業界へ身を移すのも有効
黙っていても、評価はされません。
行動して、評価をされるようになるか、評価をされる職場に移る必要があるでしょう。
(参考)業界ごとの平均年収比較(30代前半〜後半)
| 業界・業種 | 平均年収(30代前半) | 平均年収(30代後半) |
|---|---|---|
| 金融・保険業※1 | 約605万円 | 約697万円 |
| 製造業(メーカー)※1 | 約466万円 | 約529万円 |
| 情報通信業(IT)※1 | 約519万円 | 約619万円 |
| コンサルタント※2 | 約680万円 | 約740万円 |
※1「30代の平均年収・中央値はいくら?男女・業界・男女別データも」
※2「コンサルタントの年収の違いを徹底比較!役職・企業・業界別の違いと高収入の理由」
コンサルタントの仕事内容を知るための本は、こちらで紹介しています。
また、市場価値の高いスキルを身につけて、社内だけでなく社外でも評価されるようになるのもひとつの手です。
以下では、市場価値が高いとされているITスキルを身につけるためのおすすめスクールを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
5. おすすめ転職エージェント
「転職活動を始めること」と「今すぐ辞めること」はイコールではありません。
視野を広げるために動くことで、かえって「現職のよさ」に気づくこともあります。
初めての転職を考える方には、以下の転職エージェントがおすすめです。
リクルートエージェント
業界最大級の求人数。職種・業種問わず選択肢が豊富。
転職が初めての人にも丁寧なサポートが特徴です。
リクナビNEXTやリクルートダイレクトスカウトなどの連携もスムーズで、転職サイトとの相性も抜群です。
マイナビエージェント
20代〜30代の若手に強い。
キャリア相談や書類添削などが親身で、未経験からの挑戦にも強いです。
各業界に強いエージェントが在籍しているため、同業界での転職も詳しくかつ丁寧に相談に乗ってもらえます。
パーソルキャリア(doda)
リクナビ同様、圧倒的な求人数を誇る転職サイト『doda』の活用ができます。
スカウト型とエージェント型を併用でき、スピード感と情報量のバランスが良い点が魅力。
どのサービスも無料で利用でき、情報収集の一歩として登録する価値があります。
また、エージェントではないですが、転職スカウトサービスとして、「ビズリーチ」もおすすめです。
自分でも思ってもみない業界・職種・会社からのスカウトが来ることもあり、視野を広げるためにも活用してみましょう。
関連書籍
転職が選択肢の一つとして考えられる場合は、下記の書籍で転職に必要な情報を集めてみるのをおすすめします。
今の職場でいいのか迷ったら読む本、適職に就く方法、年収を上げる方法、時代の流れに乗った転職方法など様々な切り口で紹介しています。
気になる本があればぜひ手に取ってみてください。
関連記事
まとめ
評価されない原因の多くは、あなたの努力不足ではなく、環境や制度にあります。
客観的に現状を整理し、社内で改善できることは試し、それでも改善しなければ社外の市場を覗く──これが、キャリアを守るための現実的な一手です。
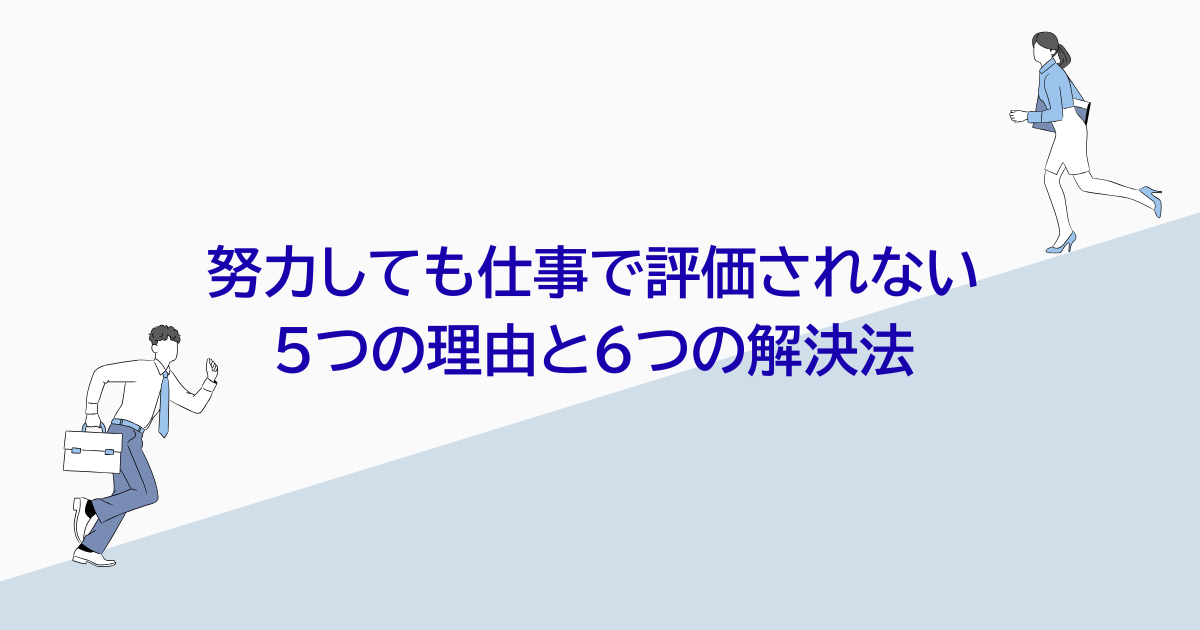
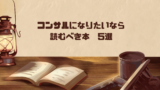
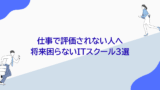
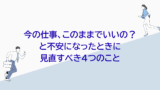
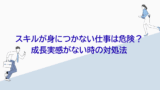
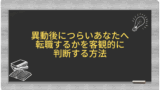
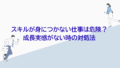

コメント