「クリティカルシンキングを学んだけど、具体的な練習方法がわからない…」
そんな悩みを抱えている人は多いはず。
抽象的な理論だけでは頭に残らず、思考のクセも変わらない。
本記事では、演繹・帰納・MECE・ピラミッド構造などを活用して、論理的に考える“思考の練習”を6つ紹介します。
- フレームで自動的に網羅できる
- 自分の主張に穴がないか検証できる
- 構造化された結果から説得力のある結論を導ける
普段の仕事や議論の場で、「論理の型が自然と使える自分」になれる一記事です。
なぜ、論理的思考の訓練が必要なのか?
クリティカルシンキングとは、問題や主張に対して論理的に構造化し、因果や前提を問う技術です。
グロービス式でも語られるように、「論点整理」「横展開」「縦の抽象度」などの思考フレームは、実務での決断を支える基礎になります。
例えば、議論の要点を言語化したいとき、
- 演繹的に主張を検証し、
- 帰納的に仮説を立てて検証し、
- MECEで整理して抜け漏れを防ぐ——
こうした型を使うことで、「説得力」と「再現性」が備わります。
思考訓練6選|論理的フレームを“使う”実践例
① 演繹法(三段論法)で論理性を検証
例:「リモートワークは生産性を上げる」
一般論:「集中できる環境=生産性向上」
特定の事象:「私は、自室が集中できる」
結論:よって、職場ではなくリモートワークは生産性が上がる
→ 問い直し:「集中できる環境」は多数に成り立つ?「生産性」は何で測る?
このように、一般的なことと特定の事象を結びつけることを演繹法といいます。
他にも
一般論:「高利益な会社はビジネスモデルが優れている」
特定の事象:「A社は売上に対し、コストがかかっていない」
結論:「A社のビジネスモデルは優れている」
高利益なことだけが物差しではないですが、企業分析で当たりをつける際などはこのように考えることもあるでしょう。
② 帰納法で仮説とデータを構築
例:「若手社員の早期離職を防ぐには?」
観察:
- 業務内容の不明確さ
- コミュニケーション不足
- 成長実感の欠如
→ 仮説:「期待と現実のギャップ」
→ 次に「1on1」「オンボーディング設計」で検証
③ MECEで要因を網羅的に整理
例:「プロジェクト遅延の原因分析」
- 人(スキル・配分)
- プロセス(見積・工程管理)
- ツール(SaaSの使い勝手)
- コミュニケーション(報連相の遅れ)
→ 対策が“漏れなく重複なく”分類できる
④ ピラミッド構造で主張を明確化
例:「新規ツール導入は費用対効果に合うか」
- 主張:導入は妥当
- 理由1:工数削減の定量効果
- 理由2:他社導入実績が成功例多
- 理由3:初期費用は半年以内に回収
→ 結論が即理解される構造へ
⑤ 反対立場から考える(逆視点の演習)
例:「リモートワーク継続は正解か」
立場:リモート推進派
逆視点で考えると:
- 若手育成機会の減少
- 雑談からの学びが減る
- セキュリティリスク
→ バランスの取れた判断が可能に
⑥ 前提検証による思考の精度向上
例:「転職した方が合っている」
主張:転職すべき
前提:成長できない/評価されない/他社の方が良い
→ 問い直し:成長とは何か?評価の基準は?他社の環境はどうか?
→ 結果:主観が前提になっていた可能性を自覚
クリティカルシンキングを身につけるおすすめサービス・書籍
クリティカルシンキングや論理的な思考を鍛えるためには、以下のサービスや書籍から学ぶのがおすすめです。
こういった思考法を活用してコミュニケーションをとることでビジネスの場では、大変重宝されます。
関連記事
まとめ:論理的思考は“型を使って磨く”
- 演繹・帰納・MECE・ピラミッド構造などの型を意識する
- 自分の主張や課題に、網羅性と論理性を担保する
- 日々の仕事・議論・資料作成などで再現的に使える技術
まずは1つ選んで日常に取り入れてみてください。
思考力が変わると、仕事の質も見え方も自然と変わります。
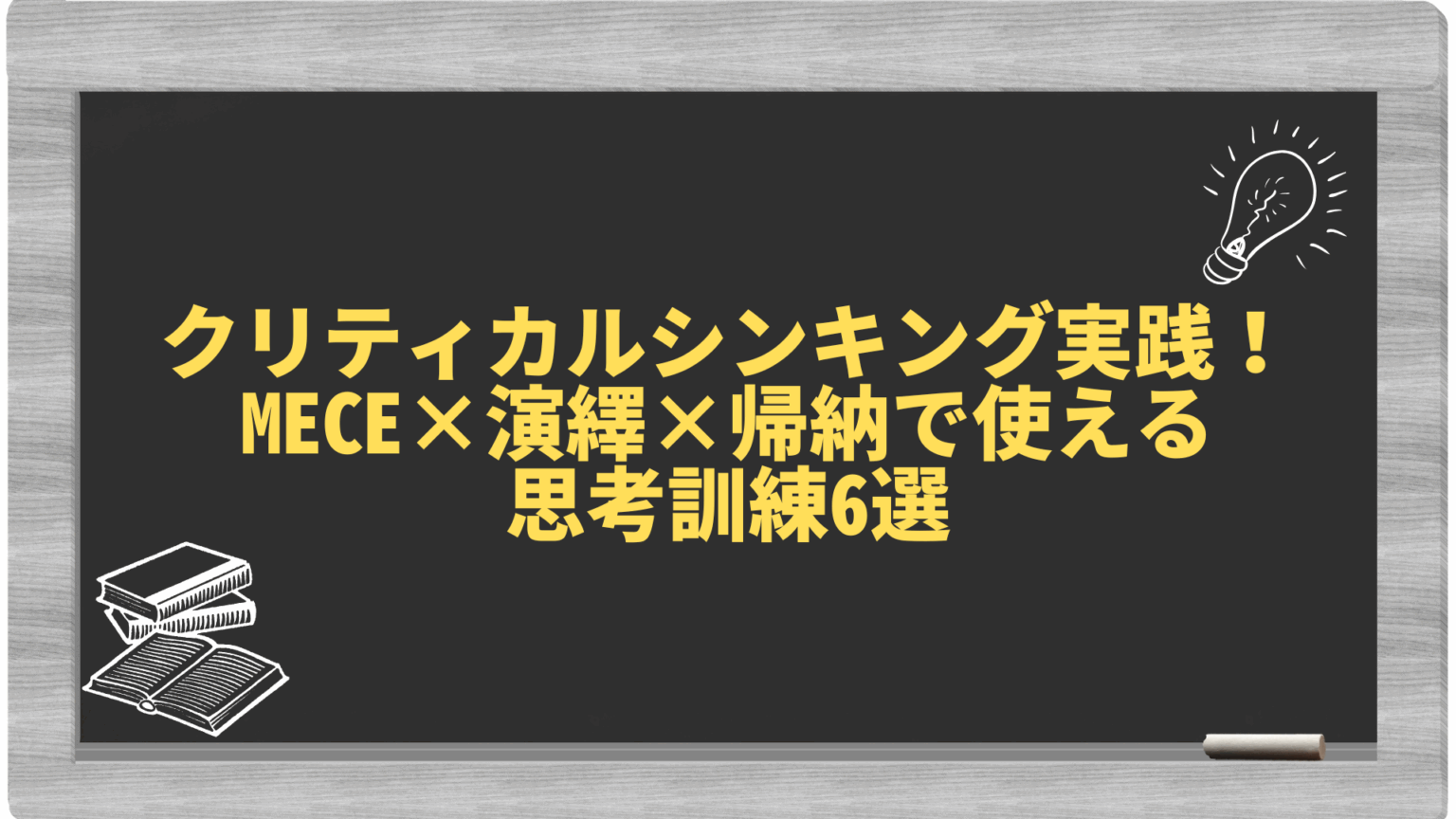
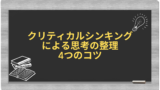
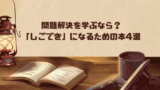
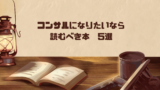
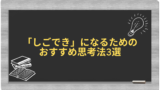
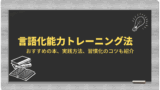
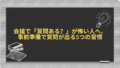
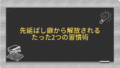
コメント