「好きを仕事にすれば、きっと毎日が充実するはず」——そんな言葉に惹かれて、仕事探しに悩んでいませんか?
しかし、実際には、
「好きなことを仕事にしたけれど、理想と現実のギャップに苦しんでいる」
「何が好きかわからないまま時間だけが過ぎている」
という声も多く聞かれます。
この記事では、「好きを仕事にすれば幸せになれる」という幻想から解放され、科学的に裏付けられた“本当に自分に合った仕事=適職”の見つけ方をお伝えします。
① 好きを仕事にすると幸せになれるか
多くの人が「好きなことを仕事にする」ことを理想とします。
しかし、実際には「好き」を追いかけることが、必ずしも幸福や成功に結びつくとは限りません。
例えば、「好きを仕事にすると情熱があるから続けられる」と思われがちですが、実際には興味だけでは長く続けることが難しい場合が多く、スキルの習得や成果も中途半端になりがちです。
また、好きなことが仕事になると義務感やプレッシャーに変わり、逆に「好きじゃなくなる」ことさえあります。
一方で、心理学の研究によると、人が仕事に情熱を感じるのは「好きだから」ではなく、「努力を注ぎ、成長や成果を感じられたとき」です。つまり、仕事を続けるうちに好きになることの方が、長期的には幸福度を高めやすいのです。
だからこそ、「好きだから」という理由だけで仕事を選ぶのではなく、自分が力を発揮できる環境や成長を実感できる職場を選ぶことが大切なのです。
② 適職に就くポイント
「好きなことがわからない」「やりたいことが見つからない」という悩みを持つ人にとって、適職をどう見つけるかは大きな課題です。
とはいえ、いきなり理想の仕事を見つけようとするのではなく、科学的な視点で「どんな条件がそろうと人は仕事に満足しやすいか?」を知ることで、自分に合った選択が見えてきます。
例えば、『科学的な適職』という書籍では、人が仕事にやりがいや幸福を感じやすい条件として、次のような要素が挙げられています。
– 自分の“焦点タイプ”(モチベーションの傾向)に合っていること
– 一つの業務に閉じず、多様なスキルや業務ができること
– 自分の仕事が誰かの役に立っている
=貢献実感があること
自分の“焦点タイプ”
「焦点タイプ」とは、成長や進歩にモチベーションを見出すタイプか、安心・安定にモチベーションを求めるタイプかを見極めます。
これにより、自分がどんなタイプの仕事に合うのかを参考にすることができます。
ほとんどの性格テストは、信憑性が低く、また、適職という観点からはデータが不十分だそうです。
しかし、「制御焦点」という焦点タイプを見極める本テストでは、コロンビア大学などの研究により、パフォーマンスアップの効果が証明されています。
テストは、16個の質問に対して1〜7段階で回答します。
それぞれの質問には、どちらのタイプに関する質問かが割り振られており、タイプ毎に合算します。
この合計値が高い方のタイプが自分のタイプとなります。
進歩や成長を求めるタイプは、コンサルタントやアーティスト、テック系、コピーライター等に関する仕事に適しています。
反対に、安心・安定を求めるタイプは、事務員や技術者、経理、データアナリスト、弁護士などが適しています。
詳細については、「科学的な適職」にて紹介してますので、ぜひお手にとってみてください。
多様なスキルや業務ができる
人は、日常の仕事においてどれだけ変化を感じられるかで幸福度が左右されます。
決まった作業の繰り返しなどでは、幸福を感じにくいのです。
では、実際にどんな変化があるといいのかというと
- スキルや能力を幅広く活かせられる
- 業務の内容が多岐にわたる
ことです。
人は誰しも同じことをやり続けると必ず飽きが来ます。
しかし、業務のかかわる範囲が広いほど、多様な仕事をするため、活用するスキルや能力に差異が出ます。
例えば、店舗販売の人であれば、現場の経験をもとに製品企画から入り込めることで、仕事の川上から川下まで関与でき、責任感の醸成もすることができます。
このように仕事の内容に変化をつけることで幸福度をあげることができます。
貢献実感がある
顧客の反応を見ることができ、貢献実感があるものが幸福度が高い仕事と言われています。
たとえば、シカゴ大学で5万人に対して30年間の追跡調査が行われたリサーチによると、最も幸福度の高い仕事トップ5は、
- 聖職者
- 理学療法士
- 消防員
- 教育関係者
- 画家・彫刻家
日本では聞き慣れないものもあり、一見バラバラに見えますが、共通点は「他人への貢献がわかりやすい」ことです。
聖職者は信者の悩みに寄り添い、理学療法士と消防員は患者や被害者を苦しみから救い、教育関係者と画家・彫刻家は情報やものの見方を提供します。
一方で、レジ打ちや倉庫ピッキングなど単純作業ばかりの仕事は、これらが悪いというわけではなく必要な仕事ではありますが、他人への貢献が感じにくく、満足度が低くなってしまいます。
これらの仕事は単体で考えるのではなく、他の業務もできるような工夫をするとよいでしょう。
上記の基準に仕事を選ぶことで、「なんとなく面白そう」や「給料が高いから」といった曖昧な基準ではなく、長く続けられて満足度の高いキャリアを築きやすくなります。
まとめ
「好きを仕事にする」ことは、悪いことではありません。
しかし、それだけを基準にして仕事を選ぶと、かえって満足できない結果になることもあります。
大切なのは、自分がどんな環境や条件で力を発揮できるかを知ること。
そのためには、感情や憧れに流されるのではなく、データや心理学的な視点から「適職」を探ることが、幸せなキャリアへの近道です。
科学的な根拠をもとに、自分に合った仕事を見つけたい方は、まず「自分の焦点タイプ」を知ることから始めてみてください。
その他、転職を考えたらおすすめの本は以下にて紹介しています。
また、本記事は「科学的な適職」をもとに紹介しております。適職の見つけ方を詳細に知りたい方は、ぜひこちらもご覧ください。
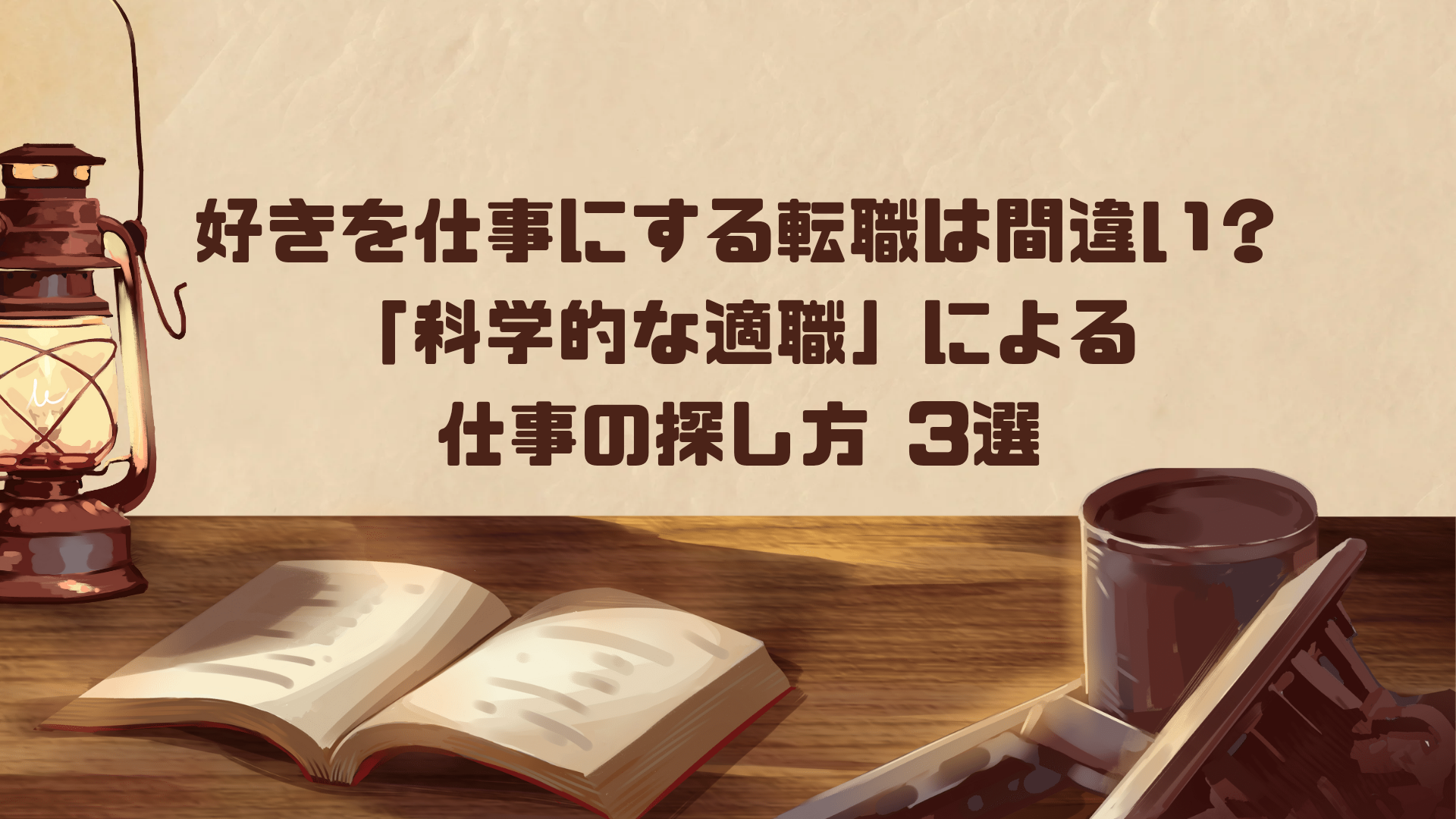
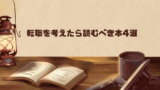
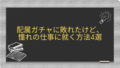
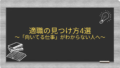
コメント