仕事をする上で「仕事に慣れてきたけど、今後どうやって成長すればいいのか?」と悩むことってありませんか?
目標設定を「数値化」して管理してみてはいかがでしょうか?
「数値化」って厳しくてきつそうなイメージがあり、何がなんでも目標数値を達成しろ!という感じがありますが、数値化は怖いものではなく、成長のための大事な目標設定方法なんです。
本記事では、著書「数値化の鬼」を元にした成長する目標設定の方法を紹介します。
圧倒的な成長をしたい人は、「数値」によって自分律し、行動量と成果を上げたくなると思うので、ぜひ参考にしてください。
0. PDCAの数値化
仕事で成長・成果を上げるためには、古典的ではありますが、「PDCA」を回すことがやはり重要です。
PDCAとは、「Plan:計画」、「Do:行動」、「Check:評価」、「Action:改善」です。
多くの人は、計画時「Plan」にテンションが上がり、計画を立てて満足してしまいますが、計画は実際に行動が伴って意味をなします。
そのため、「D」行動以降の数値化がとても重要になります。
ここで、明確な数値化をできることが会社の業績と自らの成長につながります。
数値で管理することはとても厳しく感じますが、「D」行動を達成できなかった場合は、落ち込まずに「C:評価」して「A:改善」していくことまでがセットです。
なので、次への改善を考える必要があり、部下を持つ人は達成できなかったことで部下を責めず、できなかった要因を探り、改善していく体制や目標の見直しをしましょう。
以下では、「P」の計画以降で重要な「D」行動と「A」改善にフォーカスを当てて紹介します。
1. 行動量を定める
まず、最初に「どれだけ成果数」ではなく、「何をどれだけ行うか」という行動量を定めます。
「PDCA」でいう、「Do(行動)」にあたるフェーズです。
・成果…最終的な結果、組織として求める結果。
・行動量…成果のために必要な行動。活動。
最終的な成果に対して、何をどれだけ行動する必要があるかを数値にして考えます。
例えば、営業で「上半期で、1人売上3,000万円」という目標が課されたとしましょう。
その際、顧客1人の売上が500万円、顧客を獲得するのに20人と交渉、交渉に至るまでにテレアポや訪問が100人とします。
この場合、
・テレアポ/訪問…500人
・1日に4〜5人へテレアポ
が具体的な行動となります。
このように最初に課された目標に対して、自分たちの会社では通常どれくらいの人数にアポイントとって、そのうち何人が交渉の場を設けてくれて、そのうち何人が買ってくれるかを把握し、それをもとに行動量を決めます。
ここでポイントなのが「質を求めすぎない」ことです。
多くの成功者は質もさることながら、行動量がとてつもないようです。
簡単に成功しているように見えるのも、驚くほどの行動した結果、生まれてくるもののようですが、多くの人は計画に時間をかけ行動までに時間をかけてしまいます。
つまり、圧倒的な成果をあげている人ほど、「打席数が多い」と言うことです。
そのため、上記のような目標に対して、
「毎月500万円の売上を上げる」
という漠然とした計画を立ててしまい、行動「量」ではなく、「質」を上げることに集中してしまうと、目標達成ができなくなります。
そうならないためには、上記のように日々の行動、1日の行動に迷いがないレベルにまで「KPIに分解できていること」が重要です。
KPIとは「重要業績指標」といい、目標達成に向けたプロセスの進捗状況を定量的に評価できるようにしたものです。
目標に対して、日々の行動まで「数値化」して落とし込めるかが仕事ができるかのポイントになります。
2. 改善していく
「数値化する」と聞くとかなりきつい印象を受けてしまいますが、達成できなかったら責めるのではなく、「なぜ達成できなかった」のかを考え、改善へ繋げていきます。
つまり、PDCAの「Action(改善)」です。
毎回数値化した目標を達成するのは、最初のうちはかなり難しいと思います。
しかし、達成できなかったことに関して、なぜ達成できなかった自分の行動を振り返り、改善するには何をすべきか、はたまた、「変数」を間違えていないかなど次に繋げることが重要です。
なので、なにも「絶対に達成しろ」、「どんな手段を使っても達成しろ」、「達成できない奴はクズだ」というわけではありません。
しっかり目標を数値化し、行動量を管理し、達成したら次へ、達成できなかったら次はどう改善するのかを着実に回すことが成長への近道なのです。
3.確率の罠と変数に注意
目標・計画を立てる際に確率や指標といった変数に注意が必要です。
確率の罠については、わかりやすくいうと「アポ取って8割が成約に繋がった」というものです。
同じものを売るとして、
・10件中8件で目標を達成
・100件中60件で目標は達成しなかった
場合、どちらが会社にとって良いでしょうか?
成功「率」を是とするのか、成功「数」を是とするのかと考えた時、後者の方が明らかに会社にとって良い結果をもたらしており、評価されるべきですよね。
こういったことから、確率を用いて数値化するときは、会社にとっては良い結果はどれか、行動「量」はいくらかに注意をしましょう。
また、変数に注意するというのは、自分がコントロールできるところとできないところをしっかり見極め、コントロールできるところに目を向けることです。
例えば、医療業界で働いているとすると、政策や法律で決められているところは自分ではコントロールできないのでどんなに努力しても変えようがありません(診療報酬の算定金額、医師免許等の資格の有無による可能な行為等)。
しかし、政策や法律に直接関わらない、RPAなどの業務効率化ツールなどは比較的導入がしやすいものとなっています。
このように何を変数とするかを見極めることが大事となってきます。
まとめ
仕事において、目標を数値化し、PDCAを回しながら自らを律し、成長しようというのが本書の内容でした。
そのためにはきちんと上司と話し合い、数値化した目標を立てることが重要です。
また、目標を達成できなかったときは、悲観的になりすぎず、PDCAの「A(改善)」に向けてしっかり「C(評価)」し、次に活かしましょう。
まだまだ数値化に対してのエッセンスが本書に書かれていますので、興味がありましたらぜひお手に取って読んでみてください!
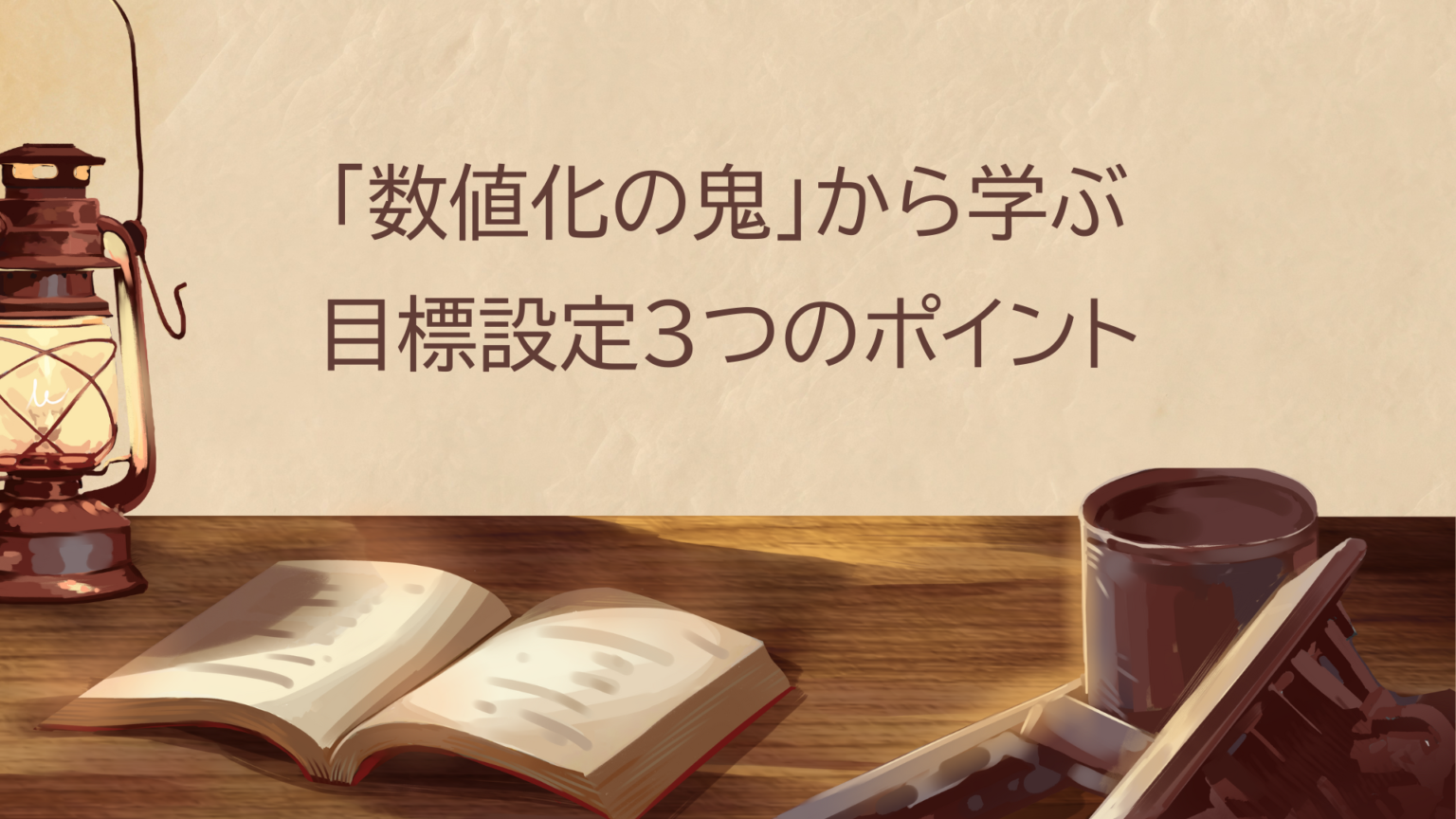
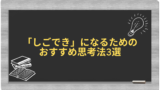
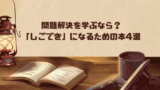
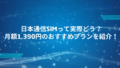
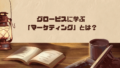
コメント