「仕事で残業までして頑張っているのに、なぜか上司から評価されない…。」
「自分は一体、何がダメなんだろう?」と悩んでいませんか?
実は、これはあなただけの問題ではありません。
リクルートマネジメントソリューションズ「テレワーク環境下における人事評価に関する意識調査」(2021年) の調査では、評価制度に不満を感じている人は4割で、「何を頑張ったら評価されるのかがあいまいだから」と言う理由が 65.1% と圧倒的に多いことがわかっています。
また、同じく 「人事評価制度に対する意識調査」(2017年発表) でも、不満の主な理由として「何を頑張ったら評価されるのかあいまいだから」「評価基準があいまいだから」といった理由が半数近くを占めています。
これらからも分かる通り、仕事のなかで評価されないと感じる人は多く、何を評価されているかわからず悩んでいる人が多いのが事実です。
つまり「頑張り方が伝わっていない」「評価軸とズレている」ことが原因で、努力が報われないケースが多いのです。
この記事を読むと、
- なぜ頑張っても評価されないのか?
- 評価される人との違いは何か?
- どうすれば評価されるようになるのか?
がわかります。
私自身もかつては「頑張っているのに評価されない人」でしたが、行動を少し変えるだけで、評価されやすい働き方ができるようになりました。
評価される方法を知り、満足いく仕事をしていきましょう!
頑張ってるのに評価されない理由と評価される人の特徴
上司の評価軸とズレている
あなたが「プロセスを評価してほしい」と思っていても、上司が「成果・アウトプット」を重視していたら評価は上がりません。
これは「頑張っても評価されない人」の一番の根本的な勘違いです。
上司の評価基準を満たさない限り、どんなに頑張っても評価はされません。
上司が「売上」なのか「利益」なのか、はたまた、「案件1つを完遂させる」のか「論文何本」、「特許何件」なのか、何を目指しているか。
それがわからない限り、何を頑張ってもその頑張りは評価されません。
評価される人は、上司が何を期待しているかを把握し、その優先順位に合わせて動いてます。
成果が正しく伝わっていない
どれだけ頑張っても、成果が数字や事例で示されなければ「伝わらない努力」になってしまいます。
評価をする際、
- 「業務を効率よくすることができました」
- 「5%の業務時間を削減でき、月に100万円のコスト削減ができました」
と言われた場合、2番の方が納得感がありますよね。
また、評価をする側になった場合、さらに上の人に説明する際に評価基準が明瞭になり説明もしやすくなります。
評価される人はこのように「売上10%UP」「業務時間を週5時間削減」など、数値や実例で可視化し、成果物・アウトプットにこだわります。
進捗共有や報告が少なく、上司が把握していない
「見ていればわかるはず」という考えは危険です。
上司も人間です。上司は基本的に忙しいので、部下の仕事っぷりをすべて見ることはできません。
例えば、多くの職場は、成果物や売上などで評価されると思います。
もし、あなたが成果物の質がイマイチ or 売上が達成できなかった場合、頑張りを認めてもらいたいというのは当然です。
しかし、それまでの経緯を共有していないと、「結果」のみでしか評価されません。
評価される人は、小さな進捗や成果でも週報・会議・雑談などでさりげなくアピールしています。
また、こうすることで上司とのすれ違いを防ぎ、早い段階での軌道修正も可能になり、より評価される結果につながるでしょう。
評価されないときの改善策【方向性を間違えないために】
ただ闇雲に頑張るだけでは状況は変わりません。
大切なのは「頑張りの方向性」を正しくすることです。
成果・進捗の伝え方を工夫する(数値×小まめな報告)
「売上を伸ばしました」ではなく「売上を前月比15%伸ばしました」と言う。
たったこれだけで、説得力が格段に上がります。
数値で示すことは、周りの人との認識の齟齬がなくなります。
これにより、説得力の向上に加えて、仕事もスムーズに進めることができます。
例えば、数値で伝えにくい仕事の場合は、全体進捗のうち何%進んでいるかでもいいでしょう。
「正確な進捗なんてわからい。進めないとどんな問題があるかわからない。」そんな場合は、ざっくりの進捗と残りのタスクは何かまで示しましょう。
これを上司と毎日、少なくとも週に一回など定期的に確認することで、上司も安心して進捗管理ができ、問題があった場合でも軌道修正ができます。
これにより、上司が求めている方向性と近くなり、自然と評価がされやすくなるでしょう。
成果や目標を数値化することの重要性やその方法については、『数値化の鬼(著・安藤広大)』がおすすめです。
数値化は、仕事の基本です。これを読んで、仕事ができる人になりましょう。
こちらで、数値化に関して解説してます。こちらもぜひ参考にしてください。
上司と1on1で期待値をすり合わせる
定期的に「自分の優先順位はこれで合っていますか?」と確認することで、評価軸のズレを防げます。
自分が100の成果だと思っていても、上司からしたら60の可能性があります。
いつまでに、何を、どれくらい達成しないといけないかを上司と握っておくことでずれを防ぎ、納得感のある評価ができるでしょう。
おすすめは、期初に半年から1年の目標値を設定し、四半期毎など小まめに上司と確認し、必要であれば軌道修正をしましょう。
それでも評価されないときの解決ステップ
①評価されにくい環境の可能性を見極める
成果を出しても評価されない職場は、制度や文化に問題があるケースがあります。
上記の改善策を試しても、上司とのウマが合わなかったり、自分の考えと会社の制度・文化と合わない場合もあります。
例えば、残業してる方が評価されたり、成果を出してる自分よりゴマ擦ってる同期のほうが昇進が早かったり…
こういった自分の価値観と合わない職場では、身も心も消費するだけになってしまいます。
そうなる前に今の職場では、どういう人がどういう基準で評価されているのかを直ちに見極めましょう。
②自分の市場価値を客観的に把握する
転職サイトの「市場価値診断」やキャリアコーチングを活用し、スキルや経験が外でどう評価されるかを知りましょう。
自分では自信がなくても、第三者と相談したり、診断を受けるなど客観的に自らのキャリアを見ることで、意外な強みやスキルを見つけられることもあります。
同じ職場で働き続けると案外自分がやってきたことの価値には気づきにくいものです。
「これまで自分はどんな仕事をしてきて、どうやって課題を解決してきたか?どんなスキルを身につけて、どんな経験をしてきたか?」キャリアの棚卸し・可視化を行い、自分の市場価値を確かめましょう。
客観的に見ると、これまでの評価が妥当だったのか、あるいは、やっぱり物足りないのかを冷静に見ることができます。
そのうえで、市場価値と今の職場が釣り合っていない場合は次のステップに移りましょう。
③転職・キャリアチェンジという選択肢
どうしても評価に納得できない場合は「職場を変える」ことも正しい戦略です。
組織の文化や制度はすぐに変えられません。
たとえ制度が変わったとしても評価者は、過去に自分が体験したことや過去の慣習に逆らえず、評価方法が変わらないこともあります。
いつ変わるかわからない評価方法にあくせくするのではなく、しっかり評価してもらえる会社を探すのが一番の特効薬です。
転職は勇気のいる行動ですが、動かない限りずっと悔しい思いやいらだちを感じることになります。
しかも、現代は、転職が当たり前の時代です。
たとえ転職先もだめな場合、また次の転職先を探せばいいのです。
市場価値の高いスキルを身につけて、社内だけでなく社外でも評価されるようになるのもひとつの手です。
以下では、市場価値が高いとされているITスキルを身につけるためのおすすめスクールを紹介しています。ぜひ参考にしてみてください。
人生は、動いた人から幸せを掴みにいきます。
現状維持が一番のリスクです。
一度きりの人生、悔いのない選択をしましょう。
まとめ
頑張っているのに評価されないのは、あなたの努力が足りないのではなく「評価されやすい形で伝わっていない」からです。「頑張りの方向性」を正すことで、評価は変わります。
今日からできる改善策はシンプルです。
- 成果を数値で見える化する
- 上司の評価基準を理解する
小さな行動を変えるだけで、あなたの頑張りはしっかり評価されるようになります。
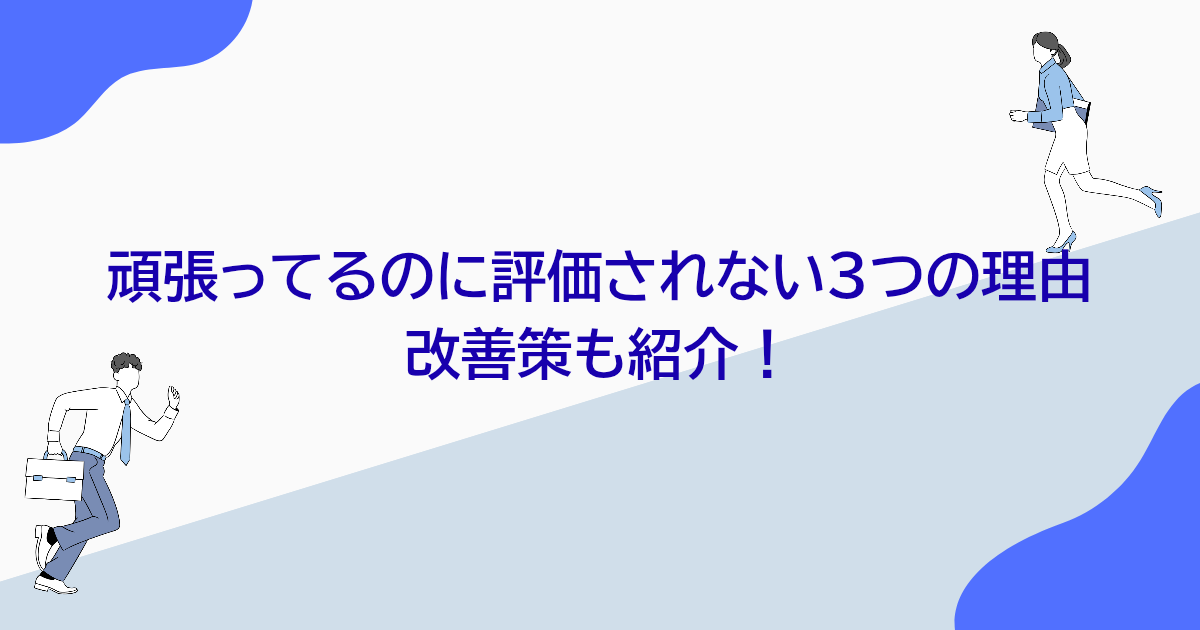
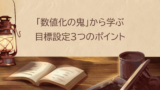
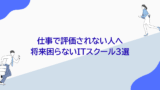
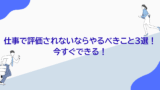
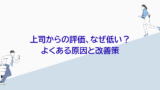
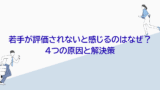
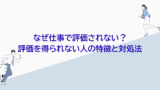
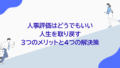
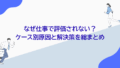
コメント