「私にはどんな仕事が向いているんだろう?」
転職を考えたとき、こんな疑問に直面したことはありませんか?
適性や強みをベースに職探しをするのは、もはや当たり前。
でも実は、その“当たり前”が、かえってあなたの選択肢を狭めてしまっているかもしれません。
本記事では、「科学的な適職」に基づいた考え方をもとに、単なる“適性診断”ではわからない、本質的な適職の探し方を4つご紹介します。
読み終える頃には、自分らしく働くための視点が一つ広がっているはずです。
「適性・強み」だけで仕事を探すのは危険?
適性や強みだけを頼りに仕事を選ぶのは、意外にも落とし穴があります。
日本で行われる面接やインターン、適性検査の多くは、その人の本当のパフォーマンスを測るのに不向きです。
なぜなら、職場ごとに求められるスキルセットは大きく異なり、評価軸もバラバラだからです。
また、有名な「ストレングスファインダー」などの診断も、科学的な裏付けはまだ弱く、自己理解の参考にはなっても、絶対的な基準とは言えません。
例えば、自己診断で「戦略性が強み」と出たからといって、すべての戦略職が向いているわけではありません。
実際には、その職場にどんな人がいて、どんな働き方が求められるかによって、活かせる場は変わってきます。
適性や強みは「参考情報」に過ぎません。
それだけで職探しをすると、ミスマッチや転職後の後悔に繋がることもあるのです。
適職の探し方
適職に近づくには、「幸福度を高める条件」を押さえることが重要です。
仕事の向き不向き以上に、「どれだけ幸せに働けるか」がキャリアの満足度を大きく左右します。
そして、幸福度を高める仕事には、以下4つの科学的に裏付けされた特徴があります。
自分の強みを持つ同僚が少ない職場を選ぶ
他人と強みが被らない環境では、自分の価値を感じやすくなり、仕事の満足度が得やすくなります。
例えば、あなたの強みが「誰とでもすぐに打ち解けられるコミュニケーション力」だとしましょう。
もし今の部署や転職先で考えている部門が「営業部」ならその強みを持った人が多くいることが考えられます。
そういった場合、自分の強みは「普通」になってしまいます。
しかし、これがベンチャーやスタートアップでの営業であれば、他にあなたと同じ強みを持つ人は少なくなるでしょう。
また、システム開発部門や管理部門など他部門や社外関係者との調整が必要な部門でも、全員が高いコミュニケーション力を持ってるとは限らないため、重宝されるかもしれません。
このように、部門内に自分と同じ強みを持つ人がいない職場は、あなたを輝かせ、満足度を高めてくれるかもしれません。
“焦点タイプ”に合った仕事を選ぶ
「焦点タイプ」とは、成長や進歩にモチベーションを見出すタイプか、安心・安定にモチベーションを求めるタイプかを見極めます。
これにより、自分がどんなタイプの仕事に合うのかを参考にすることができます。
ほとんどの性格テストは、信憑性が低く、また、適職という観点からはデータが不十分だそうです。
しかし、「制御焦点」という焦点タイプを見極める本テストでは、コロンビア大学などの研究により、パフォーマンスアップの効果が証明されています。
テストは、16個の質問に対して1〜7段階で回答します。
それぞれの質問には、どちらのタイプに関する質問かが割り振られており、タイプ毎に合算します。
この合計値が高い方のタイプが自分のタイプとなります。
進歩や成長を求めるタイプは、コンサルタントやアーティスト、テック系、コピーライター等に関する仕事に適しています。
反対に、安心・安定を求めるタイプは、事務員や技術者、経理、データアナリスト、弁護士などが適しています。
一つの適性職種に絞り込むことはできませんが、ざっくりと自分のタイプと合った仕事を見つけることができます。
多様な仕事に携われる職場を選ぶ
人は、日常の仕事においてどれだけ変化を感じられるかで幸福度が左右されます。
決まった作業の繰り返しなどでは、幸福を感じにくいのです。
では、実際にどんな変化があるといいのかというと
- スキルや能力を幅広く活かせられる
- 業務の内容が多岐にわたる
ことです。
人は誰しも同じことをやり続けると必ず飽きが来ます。
しかし、業務のかかわる範囲が広いほど、多様な仕事をするため、活用するスキルや能力に差異が出ます。
例えば、店舗販売の人であれば、現場の経験をもとに製品企画から入り込めることで、仕事の川上から川下まで関与でき、責任感の醸成もすることができます。
このように仕事の内容に変化をつけることで幸福度をあげることができます。
川上から川下まで経験できるような環境(例:企画~実行~分析まで)では、飽きにくく、学びも多いため、満足度が高まります。
貢献実感がある仕事をする
顧客の反応を見ることができ、貢献実感があるものが幸福度が高い仕事と言われています。
たとえば、シカゴ大学で5万人に対して30年間の追跡調査が行われたリサーチによると、最も幸福度の高い仕事トップ5は、
- 聖職者
- 理学療法士
- 消防員
- 教育関係者
- 画家・彫刻家
日本では聞き慣れないものもあり、一見バラバラに見えますが、共通点は「他人への貢献がわかりやすい」ことです。
聖職者は信者の悩みに寄り添い、理学療法士と消防員は患者や被害者を苦しみから救い、教育関係者と画家・彫刻家は情報やものの見方を提供します。
一方で、レジ打ちや倉庫ピッキングなど単純作業ばかりの仕事は、これらが悪いというわけではなく必要な仕事ではありますが、他人への貢献が感じにくく、満足度が低くなってしまいます。
これらの仕事は単体で考えるのではなく、他の業務もできるような工夫をするとよいでしょう。
上記の基準に仕事を選ぶことで、「なんとなく面白そう」や「給料が高いから」といった曖昧な基準ではなく、長く続けられて満足度の高いキャリアを築きやすくなります。
「この仕事が誰の役に立っているのか」が明確な仕事は、モチベーションを持続しやすく、やりがいにつながります。
まとめ
「自分に向いている仕事がわからない」と悩んでいる人ほど、“自分の適性”という言葉に縛られてしまっているものです。
しかし、適性や強みだけに頼る仕事選びには限界があります。
科学的な視点を取り入れることで、より本質的に「自分が幸せになれる仕事」を探すことができます。
焦る必要はありません。
まずは、今の仕事の中でも「多様な業務」「貢献実感」「自分の強みの活用」ができるよう、少しずつ働き方を広げてみてください。
あなたの“本当の適職”は、意外とすぐそばにあるかもしれません。
また、本記事は「科学的な適職」を元に紹介しています。
詳細を知りたい方は、ぜひお手にとって読んでみてください。
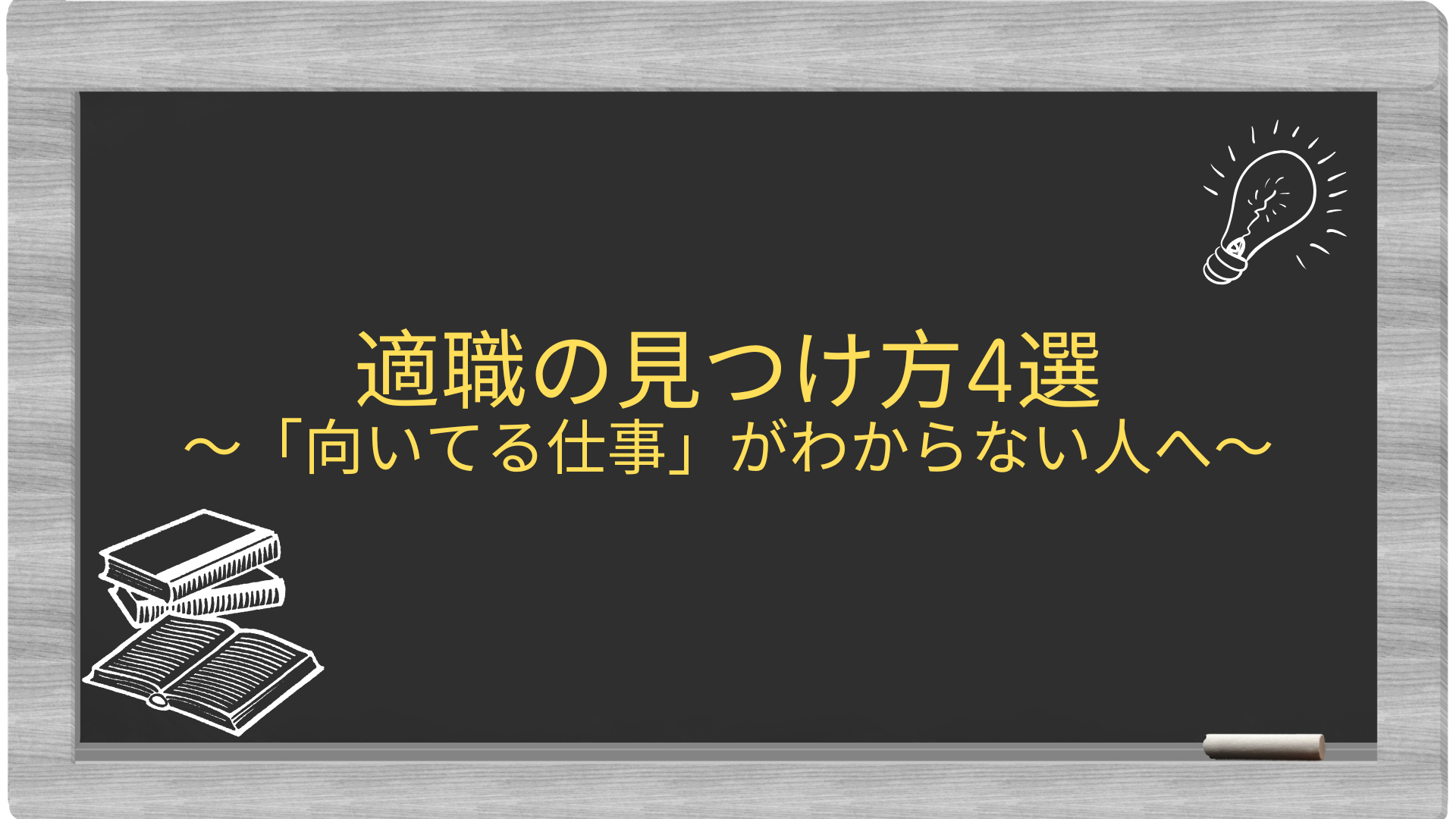
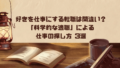
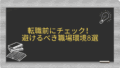
コメント